昨日、友人からいただいたものです。
今年8月中旬に噴火し、沖縄はじめ各地に漂着した話題の「軽石」です。
とうとう戸隠の山奥の博物館にも漂着しました。
長さ約8㎝、径4㎝ほどのものです。
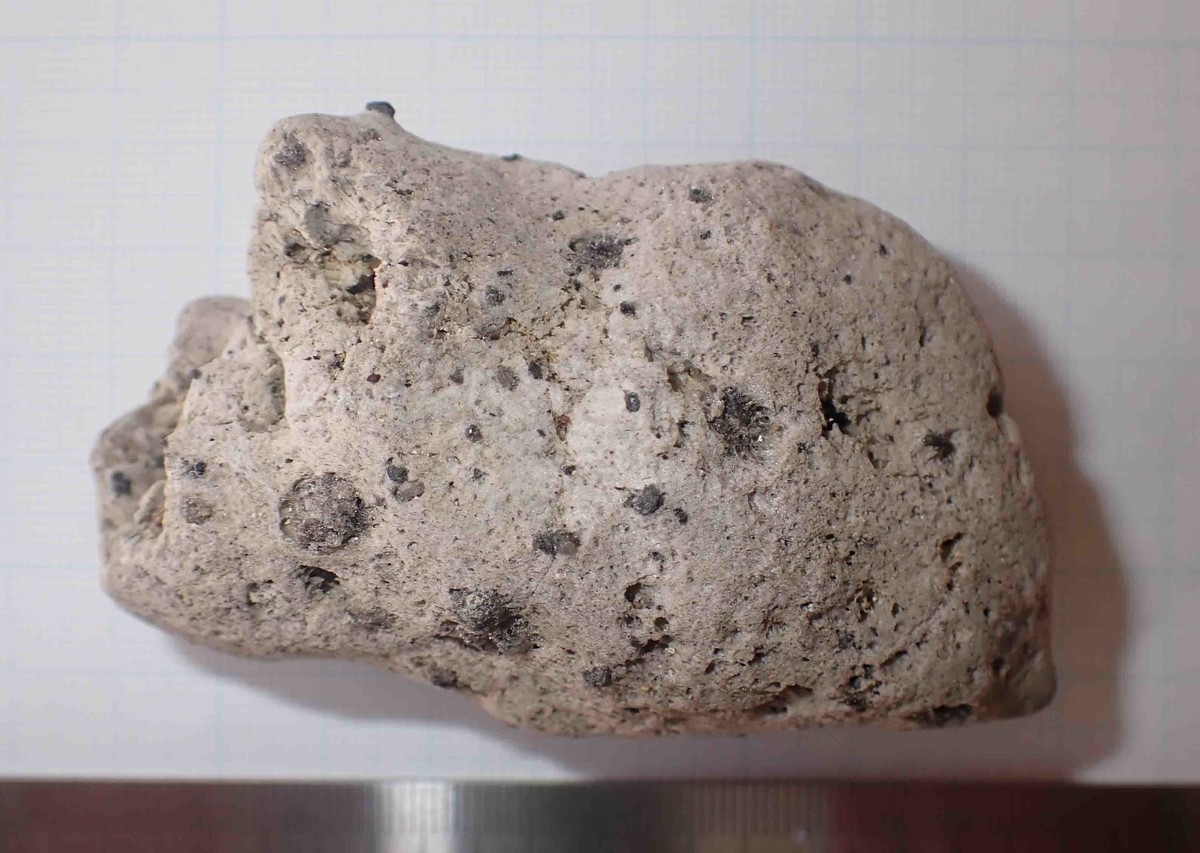
持ってみての第1印象は、やっぱり軽い…ということです。
よくみると、細かい穴がびっしりと開いています。
黒い鉱物(輝石)の結晶も結構目立ちます。
ガラス質の部分が、繊維状に見えるところもありました。

海底で火山が噴火しても、こうした発泡した岩ができるなんて、
ちょっと不思議です。
柴犬館長から、
🐕「本当に浮くのだろうか?、まず、実験じゃ!」
との、心のお達しがありました。
そこで、ガラスボウルに水を張り、比較用に瑪瑙をいれ、沈めました。
恐る恐る、軽石を入れてみると…
成功です! ぱち、ぱち、ぱち…

🐕「当たり前のことじゃ…何を寝ぼけておる…」

横からみると、よくわかります。
こんな軽石ができるなんて、一体どんなマグマだったんだろうか???
伊豆諸島から小笠原列島にかけては「玄武岩質の火山群」の
ようなイメージを持っていたので、
軽石が噴出するということにも、少々驚きます。
戸隠山や荒倉山をつくる地層の中にも、
一部、軽石質の部分もあることを思い浮かべます。
長い間には、火山の地下にあるマグマだまりにも、
変化が生じるのかもしれません。
この軽石の浮かれた様子を見ながら、今更ながらに
地下の複雑さを深く感じました…
この軽石群が、2か月もかけて日本の各地に漂着するという
ストーリーにも感動を覚えます。
🐕「海でみんなつながって居るのじゃ…」
長野盆地の西縁に露出する「裾花凝灰岩層」の中にも、
こうした軽石でできた地層がいっぱいあります。
こちらは、もっと白く、珪酸分の多い流紋岩質のものです。
風化したものは「白土」と呼ばれ、磨き砂やガラスの原料として
使われました。

松代焼の釉薬にも使われた、とのこと…
浅間山の麓には軽石流堆積物があり、小諸城の守りとなっています。
長野の銘石としてしられる「柴石」も、
こうした軽石がたくさん含まれたものでした…
🐕「やはり【柴】は最高じゃ…」
柴犬館長の心の叫びが聞こえ、どや顔が送られてきました…

今日もおあとがよろしいようで…